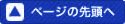当サイトはプロモーションが含まれています。
調味料や計量の基礎
美味しい食材が揃ったら、今度は料理での勝負です。食材の味を最大限に引き出せるように、美味しい味付けにしたいですね。
そのためにはまず、調味料についてしっかりと理解しておかなければなりません。調味料は料理に味や風味を加えるもので、これ無しでは料理は完成しません。
調味料には、「さしすせそ」という有名な基本事項があり、この順番に入れると良いとされています。さしすせその意味は以下のとおりです。
| さ(砂糖) | 甘味をつけるだけでなく、ツヤを出すのにも有効です。味をしみ込みやすくする働きもあるので、調理の最初に加えます。上白糖を使うのが一般的ですが、煮物には甘味が強く風味もある三温糖も使われます。 |
|---|---|
| し(塩) | まずは味付けに利用されます。その他、魚や肉の身を引き締めたり、水分を抜いたりするためにも使います。砂糖の後に使うようにします。 |
| す(お酢) | 酸味をつけるだけでなく、材料を長持ちさせる効果があります。味がまろやかな米酢、穀物で作られた穀物酢、ワインビネガーや果実酢もあります。 |
| せ(しょうゆ) | 日本人には欠かせない調味料が「しょうゆ」だと思います。塩味、風味、色、旨味などを料理にもたらしてくれます。 |
| そ(みそ) | これも和食には欠かせません。赤みそ、白みそ、八丁みそなどがあります。どのみそが良いか迷ったときは、合わせみそを選んでおけば間違いが無いと言われています。 |
また、料理を上手に作り上げるためには、調味料などの分量もしっかりと量らなければなりません。計量は、計量カップ(200ml)、スケール、計量スプーン(大さじ15ml、小さじ5ml)を使って行います。
計量カップや計量スプーンは、砂糖などの粉末の場合はふんわりと盛って表面をすりきるのが基本です。しょうゆなどの液体の場合は表面張力で盛り上がらないようにします。米用の計量カップは、1カップ180mlです。
ツイート
スポンサードリンク