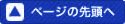鍋やカレーを作る時に出てくる「アク」の正体

鍋料理やカレーを作っている時。具材を茹でていると、必ずと言って良いほど白い塊が浮かんできます。これは「アク」と呼ばれるものであり、母親から「アクは取るもの」と教わっている人も多いのではないでしょうか。(ちなみに右の写真は、最近カレーを作った時のお鍋のアクです。)
私も母親の調理を手伝った時に「アクを取ってね!」と言われて、アクの正体が何なのかわからずにアクをおたまで取っていた記憶があります。
アクの正体についてネットで色々調べたところ、以下のような答えを得ることができました。
・野菜や肉類などの素材に含まれていた成分が、熱によって固まり、浮かび上がったもの。
・肉類を茹でた時に出るアクは、肉汁や血液が溶け出して凝固したもの。臭みの原因になる。
・野菜類のアクの正体は、シュウ酸化合物や、マグネシウム化合物、炭酸化合物などの塊。体内で石ができる結石の原因は「シュウ酸」だと言われており、アクには有害物を含む場合があるので、取った方が体に良い。
アクには肉類から出るものと、野菜類から出るものとで種類が異なることがわかりますね。肉類の場合は臭みの原因になるし、野菜類の場合は体に良くないケースがあることから、アクは取った方ばやはり無難です。
実際にアクを取った鍋料理のスープと、アクを全く取らなかった鍋料理のスープの味を比べると、その差は一目瞭然になるそうです。アクを取った方は具財の旨味や塩加減などがバランスよくまとまって美味しくなります。
しかし、アクと取らなかった方は味にまとまりがなく、塩味や甘味が強くなったりして、全体的に味にまとまりが無くなるそうです。
味噌やカレーを入れてしまえば判らなくなるといいますが、それでもアクを取るか取らないかでは味や風味に差が出ると思います。
なお、アクを取るときは小まめに取るよりも、1度にまとめて取った方が良いそうです。アクは1つにまとまる習性があるので、小まめに取ると要領が悪くなってしまいます。
料理は手間ひまをかけることで美味しくなるといいますが、アクを取ることも料理を美味しくするための技の1つなのですね。
ツイート
スポンサードリンク