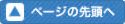当サイトはプロモーションが含まれています。
おせち料理の由来と意義
おせち料理は、昔から日本に伝わる伝統的なお料理です。年には干支があり、その年の神様が訪れて、年が新しく生まれ変わるものです。
それぞれの年の神様は「年神」と言われており、これは濃耕や豊作をもたらす神様だと言われています。
農業は人間が生きていくためには必要不可欠な業種であり、昔は日本の中心産業でした。従ってお正月におせち料理を作っておもてなしすることで、その年の豊作を願っていたのです。
おせち料理はもともと、その年の神様に供えるための料理だったと言います。日本では昔から、収穫したものを神様に供える習慣がありました。その見返りとして、次の一年の豊作を教授しているという考え方がありました。
お正月には門松を飾る慣例がありますが、これは神様が降りてくるための目印としての役割を果たしています。
もともと、お供え物としての料理は乾物が多く、そのまま食べられるものではありませんでした。これが私達人間が食べられる「おせち料理」に変化したのは、江戸時代からだと言われています。
お正月の定番メニューの一つに数の子がありますが、これは卵の数が多いことから、子孫繁栄を意味しています。
田作りというごまめは、昔は田植えの祝いの肴として使われていました。このため、おせち料理には必要不可欠な存在になっています。黒豆は、今年も健康でマメに働けるようにという願いが込められています。
なお、お正月の祝い肴は、普通は数の子、黒豆、ごまめを指しています。 今人気のおせち料理通販「匠本舗」 公式サイトはこちら↓
今人気のおせち料理通販「匠本舗」 公式サイトはこちら↓![]()
スポンサードリンク